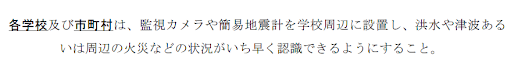最終報告案で報告されたもの② 監視カメラ
最終報告案は、第6章に「提言」がまとめてあります。
たとえば提言11の中に「各学校及び市町村は、監視カメラや簡易地震計を学校周辺に設置」という部分があります。
間違いではありませんが、大川小の事故から導き出される提言でもありません。
子ども達を守れなかったのは、監視カメラがなかったためなのでしょうか。
私たちは、今回の検証の内容が、遺族の気持ちに応えるのはもちろん、学校現場にほんとうに役立つものとなることを願い、事故直後からの様々な情報を検証委員会に提供してきました。
しかし、検証内容には、それが反映されず、曖昧なことや、事実と違う部分もだいぶあります。その上で24もの提言が出されているのです。
土台となるべき事実がグラグラしたままでは、しっかりした提言はできないと思います。子どもの命は戻ってきませんが、せめて、後世に役立てていただきたいのです。
24の提言
24の提言
最終報告案で報告されたもの③ 山の斜度
報告書案のP.27~29に山の斜度についての記載があります。斜面はポンプ小屋裏A、崖崩れ防止工事をしたB、椎茸栽培が行われていたCの三カ所に分けて書いてあります。
「いずれの斜面においても、ふもとから100mほど入る付近までの平均斜度は20°を超え、最大斜度は30°を超える」平均斜度と最大斜度だけの記載です。
しかし、多くの保護者が登って逃げているだろうと考えていた体育館裏の「椎茸栽培の山(C)」は約9°です。子どもはもちろん、高齢者でも登れます。
しかも、助かった児童が駆け上ったのは最大斜度30度の斜面Aですし、事故の数ヶ月前に低学年の授業で登っていた山(斜面B)もややきつい傾斜でした。
迎えに来た保護者がカーラジオで聞いた内容を伝え、「あの山に逃げて」と訴えています。授業で登ったことのある児童はもちろん、登れる山であることは全員が認識していました。這いつくばって、泥だらけになりながら、道のない急な山を登って避難した学校がいくつもあります。
山を選択しなかった理由は斜度ではないのです。
2014.3.17「委員長、それはないでしょう」
最終報告案で報告されたもの④ 指揮台の上のラジオ
ラジオは緊迫した口調で、さかんに避難を呼びかけていました。
指揮台の上にラジオがあり、聞いていたという証言が複数あります。
子どもたちが津波がくる心配を口にしています。「山さ逃げよう」と進言する子どももいました。
ところが最終報告書では「職員室のラジオは落下して使えない状態」「ラジオを聞いていないという証言もある」などと「ラジオを聞いていた」ことを断定せず「聞いていた可能性は否定できない」という表現になっています。
中間とりまとめでは「備品台帳に『ラジオ』という記載はない」と報告しました。
(もともと、ラジオやラジカセは台帳に記載しません)
ラジオを聞いていたのは確実。
ラジオは避難するに値する情報を伝えていたかどうかを分析すべきなのに、なぜかラジオを聞いていたかどうかを曖昧にしています。
ラジオは避難するに値する情報を伝えていたかどうかを分析すべきなのに、なぜかラジオを聞いていたかどうかを曖昧にしています。
子ども達は校庭で津波の心配をさかんに口にしています。
「子どもさえ危機感を抱かせる情報が入っていた」のです。
ラジオ・防災無線いずれかによるものとしても、児童が大津波警報を知っていて、
山への避難も進言しています。
迎えに来た保護者もラジオの情報を伝えています。
校庭にいるすべての人は「大津波警報」を知っていた。
それに対する対応をしなかったのはなぜか。知りたいのはその先なのです。
検証委員会ではその先の議論がされていません。
ラジオを聞いていたかどうか
「山さ逃げよう」という子どもがいたかどうか
津波の到達がいつだったか
2年以上前に明らかになっているこれらのことを
わざわざ曖昧なものにしています。だから議論ができないのです。
津波の到達時間についても
15時35分に家を出て助かった人がいて
15時37分に時計が止まっている
子どもにでも分かることです。それをわざわざ曖昧にしています。
ラジオを聞いていて、「山へ」という先生、保護者、子どもの進言があったにもかかわらず、避難が出来なかったのはなぜなのかを考察すべきです。そのために集められた専門の先生方のはずです。
ラジオを聞いていたかどうか
「山さ逃げよう」という子どもがいたかどうか
津波の到達がいつだったか
2年以上前に明らかになっているこれらのことを
わざわざ曖昧なものにしています。だから議論ができないのです。
津波の到達時間についても
15時35分に家を出て助かった人がいて
15時37分に時計が止まっている
子どもにでも分かることです。それをわざわざ曖昧にしています。
ラジオを聞いていて、「山へ」という先生、保護者、子どもの進言があったにもかかわらず、避難が出来なかったのはなぜなのかを考察すべきです。そのために集められた専門の先生方のはずです。
議論できないのでしょうか、それともあえて、議論をしないのでしょうか。
最終報告案で報告されたもの⑤ 子どもは判断していた
誰もいない校庭で
あの日の校庭を思います。
警報やラジオが鳴り響く、寒い校庭を思います。
それだけで、逃げ出したくなります。
子供たちは山への避難を訴えていました。
山へ走った子もいましたが、列に戻されています。
大人は自分の意思で逃げることができます。
でも、ここは学校です。
子供は逃げたくても、指示を待つしかなかったのです。
70数名の小学生を前にした、11人の先生のうち誰かが「逃げるぞ!」と言うのを
じっと待っていたと思います。
子供たちの恐怖を思えば、
その事実から目を背けてはなりません。
検証委員会では避難を進言した保護者や子供のことは、複数の証言があったにも関わらず認めず、検証の材料にはしませんでした。
そして提言にこうあります。「子供を指示の対象・受身の立場に置くやり方では、災害時に主体的に動くことのできる子供は育成できない。子供が自ら判断・行動する能力を身につけるためには・・・」
どうして、こんな文章になるのでしょうか。子供は判断していたのに…。
 |
| 朝日新聞2011.9.30 |
 |
| 河北新報 2011.9.8 |
最終報告案で報告されたもの⑥ 「推定される」
報告書を読む前に注意点。
「ほぼ間違いない場合」は
「推定される」なのだそうです。
違うと思いますが…。
「ほぼ間違いない」と書けないのでしょうか。